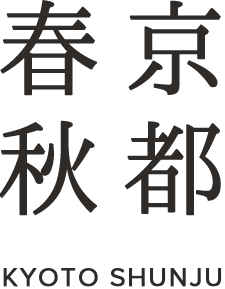法堂内狩野探幽筆『雲龍図』重要文化財
『本朝無双之禅苑』
⼤徳寺本坊 伽藍特別公開【経蔵 初公開】
2024年4月25日~6月2日
※内容が変更になる場合があります。
詳しくは「拝観のご案内・ご注意事項」をご参照ください。
後醍醐天皇から「本朝無双之禅苑」と評された禅宗の名刹、⼤徳寺は⼤燈国師によって1326年に創建されました。⼀休宗純や沢庵宗彭などの名僧を輩出したほか、千利休や狩野永徳など後世の⽇本⽂化に多⼤な影響を及ぼした⼈物たちが活躍した場でもあり、数多くの貴重な⽂化財を今に伝えます。本公開では仏殿(重文)の内部や狩野探幽が『雲⿓図』を描いた法堂(重文)の内部、聚楽第の遺構と伝わる国宝の唐⾨、また千利休が寄進した⾦⽑閣(重⽂)を間近で拝観するなど、⾮公開区域の伽藍の数々を解説付きのツアー形式でご案内します。特に今回は、初公開となる経蔵(重文)の拝観や、⾦⽑閣をくぐり間近で歴史的建造物を拝観するなど、貴重な体験ができる特別公開です。 ※個人のご拝観者様は予約制ではありません。必ず下記の「拝観のご案内」「ご注意事項」をご一読の上、ご来寺ください。
拝観受付場所:大徳寺茶所(大徳寺境内図)
20分毎に約20名様ごとに入場、ツアー形式で拝観
※個人のご拝観者様は予約制ではありません。当日先着順でご案内いたします。

三門「金毛閣」(重要文化財)
三⾨とは空⾨、無相⾨、無作⾨の三解脱⾨のことを指します。⼤徳寺の三⾨は応仁の乱で焼け落ちた後、⼤永6年(1526)に⼀休和尚参徒の連歌師宗⻑の寄進により、初層部分が完成されました。その60年後、千利休によって⼆層部分が完成し、⾦⽑閣と名づけられました。この楼上に草鞋を履いた利休像を安置したことで秀吉の怒りを買い、利休の切腹の⼀因になったのはあまりにも有名です。今回は、三⾨下をくぐり間近で拝観する機会をご⽤意しています。


仏殿(重要文化財)
現在の仏殿は文明11 年(1479)一休和尚の参徒 尾和宗臨により建立されました。さらに寛文5 年(1665) 那波常有が再建して、現在に至ります。御本尊の釈迦如来像は約190 センチで、4代将軍徳川家綱公の寄進によるものです。典型的な禅宗様で鏡天井の天井画は飛天が描かれており、狩野元信筆と伝わります。


法堂内狩野探幽筆『雲龍図』(重要文化財)
法堂(はっとう)は、禅宗寺院において⻑⽼が修⾏者に法を説くための建物で、教えを継ぐことを重要視する禅宗にとっては⾮常に神聖な場所です。ここによく描かれるのが⿓。⿓は仏法を守護し、法の⾬(仏法の教え)を降らせると共に、⽔を司ることから「⽕災から寺院を守る」ものでもあります。⼤徳寺法堂の『雲⿓図』は狩野探幽が35歳のときに描きました。真下で⼿を叩くと⿓が鳴いたように響くことから「鳴き⿓」とも称されます。


【初公開】経蔵(重要文化財)
「経蔵」は、寛永13年(1636)に建立された伽藍の一つ。江戸前期の京都の大富豪、那波宗旦の寄進により開山大燈国師三百年忌に現在の法堂と同時期に建立されました。堂内中心には八角輪蔵があり、一切経など経典約3,500冊が収められており、その約半分が平安時代後期から鎌倉時代の経典と伝わります。輪蔵を一回転させると、ここにあるお経を全て唱えたことと 同じ功徳があるといわれています。(※公開時は文化財保護のため回転いたしません)輪蔵の前には傳大士および二童子が祀られています。


唐門(国宝)
⼤徳寺の唐⾨は別名「⽇暮⾨」といわれ、国宝に指定されています。桃⼭建築の代表作で聚落第の遺構と⾔い伝えられ、桃⼭の三唐⾨(本願寺、豊国神社)の⼀つに数えられています。彫刻を観賞しているだけで日が暮れてしまう、という所から「⽇暮⾨」と名付けられた様です。平成11年から14年までの3年間をかけて修復を施し、再び美しく当時の輝きを取り戻しました。麒麟や孔雀、牡丹、波など、様々な動植物や天然物の彫刻が約40種類、⾊鮮やかに施されています。

沿革
臨済宗大徳寺派の大本山。大燈国師(宗峰妙超)が紫草の茂る洛北の野原に大徳庵という小庵を結んだことに始まります。大燈国師の教えは次第に世に知られるようになり、後に花園・後醍醐両天皇の帰依を受け、勅願所として嘉暦元年(1326)に現在の龍宝山大徳寺と命名されました。
室町時代には幕府から冷遇されますが、それが厳しい禅風を残す要因ともなって優れた禅僧を多数輩出し、桃山時代には豊臣秀吉や前田利家、細川忠興など多くの大名が自らの帰依した禅僧を開祖として塔頭寺院を創建しました。千利休が建てた金毛閣は、この楼上に利休の木像を置いたことから秀吉の逆鱗に触れ、利休切腹の一因になったことでも知られています。

三門「金毛閣」(重要文化財)
拝観のご案内ADMISSION
- 拝観期間
- 2024年4⽉25⽇(⽊)〜6⽉2⽇(⽇)
- 公開内容
- 三門「⾦⽑閣」(重要文化財)※外観のみ
- 仏殿(重要文化財)
- 法堂並びに狩野探幽筆 法堂天井画『雲⿓図』(重要文化財)
- 【初公開】経蔵(重要文化財)
- 唐⾨(国宝)
※拝観受付場所:大徳寺茶所(大徳寺境内図) ※20分毎に約20名様ごとに入場、ツアー形式で拝観 ※個人のご拝観者様は予約制ではありません。当日先着順でご案内いたします。 ※内容が変更になる場合もございます- 拝観休止日
- なし
※法務の都合により拝観休止が増える場合があります
- 拝観時間
- 10:00~15:40(受付終了)
※混雑状況により受付終了時間を早める場合あり
※20分毎に約20名様ごとに入場、ツアー形式で拝観 - 拝観料
- ⼤⼈3,000円・高校生1,000円・⼩中学生500円(保護者同伴) ※未就学児1名につき保護者1名同伴
- ご連絡先
- 京都春秋
TEL 075-231-7015 / FAX 075-231-6420
Emailでのお問合せはコチラから - ご注意事項
- 以下の事項について、予めご了承ください。
- 拝観内容が変更または中止になる場合があります。
- 境内は撮影禁止です。
- 20分毎に約20名程度の入場、ツアー形式で拝観です。
- 入れ替え制の為、拝観エリア内に留まることはできません。
- 拝観所要時間は約70分です。
- 混雑状況により門前でお待ちいただくことや、受付終了時間を早める場合があります。
- 11:00~、13:00~、14:00~は団体の方をお入れするため、団体予約が入っている場合はその間、お待ちいただきます。予めご了承ください。
- 建物の構造上、車いすでの拝観はできません。
- 拝観に随行される講師の方や先生の解説はご遠慮ください。
- 境内ではスタッフの指示に従ってください。拝観の妨げになると判断した場合は、拝観料をご返納の上、お引き取りいただきます。
- 暴風警報や大雨警報、地震などにより、拝観に来られる方に危険と判断した際は、事前の予告なく拝観休止とさせていただきます。休止を決定した時点で当HPやFacebook、Twitterにてお知らせいたします。
- 急な法務により拝観休止となる場合がございます。
【団体拝観について】
10名以上の団体様は事前予約をお願いいたします。団体予約のお受け入れ時間は1日3回限定で11:00の回、13:00の回、14:00の回です。
団体拝観を検討されている方は大徳寺本坊伽藍特別公開 団体拝観予約受け入れ概要をご確認の上、予約先/京都春秋 FAX 075-231-6420、または本サイトの団体拝観ご予約ページから予約をお願いいたします。
交通案内ACCESS
所在地
⼤徳寺本坊 伽藍特別公開【経蔵 初公開】 京都市北区紫野大徳寺町53
電車、バスでお越しの方
- 京都駅から地下鉄と市バス
- 地下鉄烏丸線京都駅から国際会館行き→北大路駅下車
北大路バスターミナル青のりばから市バス1・M1・北8・204・205・206系統大徳寺前下車徒歩約7分【目安35分】
- 地下鉄烏丸線京都駅から国際会館行き→北大路駅下車
- 京都駅烏丸口から市バス
- A3のりばから市バス206系統 千本通、北大路バスターミナル行き大徳寺前下車徒歩約7分【目安時間45分】
- B3のりばから市バス205系統 西大路通、金閣寺・北大路バスターミナル行き大徳寺前下車徒歩約7分【目安時間55分】
- 京阪電車出町柳駅から市バス
- 出町柳駅前から市バス1系統 西賀茂車庫行き大徳寺前下車徒歩約7分【目安時間30分】
- 阪急大宮駅、嵐電大宮駅から市バス
- 四条大宮から市バス206系統 大徳寺・北大路バスターミナル行き大徳寺前下車徒歩約7分【目安時間35分】
お車・タクシーでお越しの方
京都駅から約30分、地下鉄北大路駅から約5分。大徳寺総門(旧大宮通り沿い)南側に有料駐車場有り